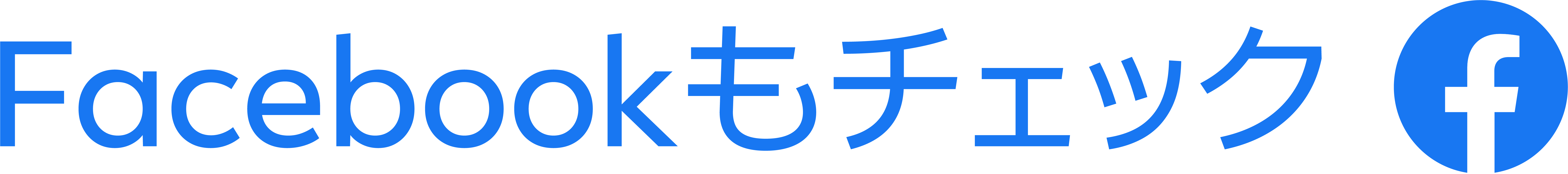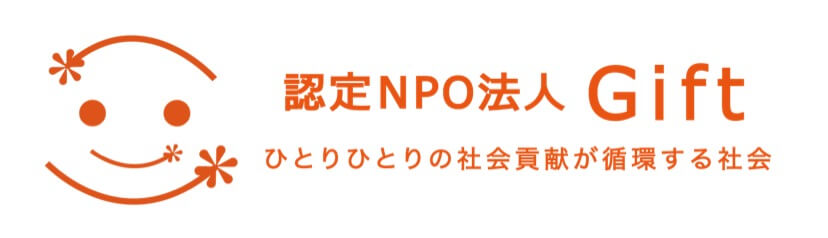多様な子供と一緒に育てば、共生社会を作っていける。インクルーシブ教育が本当にできれば、社会は変わる。
共通の友人であるユニバーサルデザインアドバイザー
松森果林さんのご紹介で私のメルマガに興味を持たれた
大西さんとご縁が繋がりました。

千葉県在住の大西紀子さん
お子さんがいて、働かれてい
るので電話取材も難しく、
メールインタビューでした
境界域特有の難しさ
大西さんには、軽度の知的障害がある、
現在中学生のお嬢さんがいらっしゃいます。
育児についての熱い思いを、
経験談談と共に具体的に語ってくださいました。
■学校の友達も先生も親である私まで娘の状態が分からず戸惑った
小さい頃ははっきり障害と分からないのに対し、
現在は分かる障害特性から、
成長段階に応じて、戸惑いの質が変化する。
幼稚園までは、「ちょっと発達が遅い子」
という周りの認識で、周りの子供たちや
ママ友との関わり方に神経を遣う。
子供特有の様々な素朴な疑問に、
どう答えるかやお嬢さんの個性を、
つぶすことなくありのままに育てたい
というご自身の思いから、靴を履くことを嫌がっても、
裸足で中庭を歩かせたりして周りから浮いてしまうことに
戸惑う日々が小学校低学年でも続いたそうです。
同じクラスの子供は先生に、先生は大西さんに質問。
でも、大西さんにもわからない。
■小学校の頃までの悩みは 見た目で障害児とは全く分からず周囲の理解が得にくいこと
ただただ、「発達が遅い」と言う説明を繰り返す。
できることはあるけど、みんなと何か違う。
算数と運動が苦手。
黙っていれば、中学受験する優秀な子だと思われる。
とにかく見た目では全く分からない手のかからない子
という周囲の評価。
そこで、自ら「発達が遅く、障害があるかもしれない!」
と先生との面談の日々。
周囲からは「思い込みすぎ」と言われる。
「見た目ではわからないので周囲の理解が難しいのが悩みだった」
と大西さん。
■中学で支援級に入り、障害は認識されたが、壁を感じた
お嬢さんは現在、発達相談や検査を繰り返し、療育手帳を取得。
中学校の支援級に在籍。
「支援級」という名前を出すと、
「障害者」と認識される不思議。
障害がありながら、普通学級だと理解されず、
「支援級」に入ると「障害者」と認識される。
認識される良さと共に壁を感じるように。
障害者とわかり、はれ物に触るように対応してくる人に戸惑った、
と戸惑いの質が変化します。
お嬢さんの入学された支援級では、
個人に合った学習レベルで対応すると
入学時説明があったが、障害者はひとくくりの現実。
支援級はトレーニングと作業がメインでずっと作業。
■境界域特有の難しさがあるからこそ、 居場所を作っていかないといけない
境界域ということで、できることもあるのに、
学習が制約される状況に対する戸惑い。
普通クラスか支援級かの二者択一。
間を行ったり来たり、うまくできる方法はないかと学校側と面談を繰り返し、模索。
たまに、親である私でさえ、「ほんとに障害があるの?」と思います。
だからこそ、声を上げなければいけないし、
しっかりサポートする必要があると思います。
居場所がない娘のために理解を求め、境界域にいる子供たちの居場所
を作っていかなければと思っています。
障害認定の現場
素朴な疑問として、このような場合、
いつの時点で、単なる発達の遅れではないとなるのか?
大西さんのお嬢さんの場合は以下のような感じ。
小さい頃から周りの同じ年齢の子供たちと発達が違うと思っていたが、
市の定期健診でも、総合病院の発達外来でも
幼少期は「小さいから診断は慎重に」ということで様子見。
■診断名がつくものだとばかり思っていた娘が
「知的障害」に入ると初めてわかり、びっくり
体験会を申し込むと市から自動的に「知的支援学級」の案内が。
ここで大西さんはまた調べ、IQの数値により
「知的支援学級」に分類されることを 初めて知ります。
「知的障害」という言葉に入ることが初めてわかったのはこの時点で
びっくりしたそうです。更に、医師に診断してもらい、
療育手帳がないと「知的支援学級」に入れない事も知ります。
慌てて小学校6年生の秋に病院を探すもなかなか予約が取れない。
友人のつてでやっと受診できた病院で
「軽度の精神発達遅滞 広汎性発達障害の疑い」
という診断書が11月に出る。
その後、診断書をもって療育手帳を申請。
簡単に受診できないのは専門医のいる医療機関が少ないから。
この分野の専門家は不足していて、
専門機関の利用にもかなり時間がかかるそうです。
中学入学までの過程のまとめ
生後3か月ごろから、何か違うと思いはじめ
3歳ごろまで発達が遅い、みんなと違う何かがあると疑い
小学校1年生からはグレーゾーンにいる
(障害と障害を持っていない状態の中間のような曖昧な認識)
小学校3年生でIQ63、
小学校6年生の春にIQ57
小学校6年生の秋に病院で診断、療育手帳取得
■言葉はたくさんあるが
紆余曲折を経て、軽度の知的障害で療育手帳を取得したお嬢さん
そもそも「軽度の精神発達遅滞広汎性発達障害の疑い」
というのは、他にもある様々な診断名とどう違うのか?
大西さん自身もわからないと率直に語られました。
自閉症スペクトラム、知的障害、
精神発達遅滞、広汎性発達障害
知的障害を伴わない発達障害、
発達障害、アスペルガー、
言葉はたくさんあります。
はっきりと、どれに入るのかは
よくわからない。
特徴としては、計算がほぼできない
コミュニケーションが苦手、
同じことを繰り返すことで安心する
臨機応変が苦手、こだわりが強い
時間の感覚が違う
お金の計算ができないなど。
何に困って、何が得意なのか?
大西さんでも時々見失う。
※障害の有無に関わらず、育児の悩みは尽きないかと思います。
ただ、とりわけ障害児でかつはっきりと障害と分からない状況が
どれだけ不安かが伝わってきました。
人間は、未知の状態に置かれると、
とても不安定になります。
その中で大西さんの「診断名が付くものと思っていた」
という言葉は本音でしょう。
しかし、同時に、色んな障害名や診断名の違いが
よく分からないとも。これは重要な示唆を与えています。
どういう名称で分類されるかでその子の
ある程度の傾向や特徴を知り、必要なサポートを考える材料とする。
医療の分野に頼れるのはここまでで、
その情報をどう育児に生かしていくか。
また、必ずしもパターン化できないので
あまりに診断名にとらわれることなく、
目の前の子供をしっかり見ることが
大切なのではないかと思いました。
療育手帳の取得で変わること 変わらないこと
知的障害の認定については、各都道府県等が交付基準を定めています。
その結果、療育手帳(地域によって名称は異なる)を取得すれば、
当事者としては、福祉制度の恩恵があるというある種の メリットがあると、
身体障害者手帳所持者の私は思います。
■手帳があれば説明が容易?
「娘は軽度なので、我が家では、
手帳については葛藤がありました。
手帳を取得したいと強く思っていた時期が
小学校入学直後にあった」
と大西さん。
周りへの説明の根拠とはっきりとした診断名
が欲しかったとのこと。
「発達が遅い」と説明することに
不安があったからです。
「障害」や「手帳」という言葉がないと、
周囲に理解されにくい。
でも、その時は手帳の種類も 、
福祉制度の恩恵も全く知らなかった。
「手帳=障害者の認定」→周囲への説明が
容易にできるという認識。
また、手帳を取得すれば、普通クラスにいても、
学校側の配慮があると思っていた。
で、小学校入学直後に手帳を取得しよう
と考えていた大西さん。
■手帳の有無にかかわらずやるべきことは同じ?
しかし、ご主人は反対でした。
「娘は娘であって、
(周囲への説明、家庭での療育的な事など)
手帳を取っても、取らなくても
やらなければならないことは変わらない。
それに、娘自身は、
「手帳を取っても取らなくても、何も変わらない」と。
我が家は「手帳取得による福祉制度上の恩恵」
には考えが及んでいませんでした。
ご主人には、「手帳の取得=障害者」
→差別されるのでは、という不安があり、
これから普通クラスで頑張れば、
「障害ではなく、個性としてやっていける!
だから手帳は取得しない」という考え。
結果的に、手帳を取得しない方針に。
しかし、高学年になるにつれて、
周りの子供たちとの差は開いていく。
進路を考えたときに、
支援学級が視野に入り、
前述の知的支援学級に入るには手帳取得が要件と知る。
そこで、小学校6年生の後半、慌てて手帳を取得。
その時に、学んた事。
おおむねIQ70未満までが知的障害
に該当する事→厚労省サイト。
地域の児童相談所で検査→市役所で申請→交付。
とにかく疑問だらけで、まずは病院を探し、診断書取得。
(大西)
病院では、今までの発達の状態を記入式の質問に回答し、
医師との面談は数分だけ。あとは保護者と医師とのやり取り。
その面談というか診察を数回繰り返して、
診断書が出ました。
児童相談所では親子が別室で検査に回答。
特に、詳しい聞き取り調査はなく、
その後10分程の医師との面談で検査終了。
教育センターで受けた2回分の 検査結果と医師の診断書を渡しました。
最後に受付で「ボーダーラインにいるので、会議にかけられるかもしれません。
そうなると、手帳が発行されるかどうかわかりません。」と言われました。
あとで、同じような子供を持つママ友に聞いたら、
「医師の面談で、どうしても手帳が欲しい。
すごく困っている、と頼み込めば大丈夫」
と聞きました。
本当にびっくりで、頼み込めば取れる なら悲しい
と感じたのを覚えています。
■手帳を取得して制度の恩恵が分かった
手帳を取得してから、娘が社会的に
「障害者」になったと実感したそうです。
娘が変わったのではないし、
関わる人も変わっていない。
これはお嬢さんの社会での位置が
実質的に変わったということです。
毎月の補助金、中学校入学時の給付金、
レジャーランドの割引、駐車場の割引等
「福祉制度の恩恵」を認識する瞬間。
しかし、“手帳初心者”の大西さんは、
「恩恵」を素直に受け入れられませんでした。
娘は娘であって何も変わっていないのに、
いつも行く動物園が無料!?
しかも、最初はそれに気付かず、
普通料金を払っていたそうで、
気が付いてからも、しばらく使えなかった。
お嬢さんは変わってないのに、
障害認定により無料ということに混乱したそうです。
また、中学の支援学級に入学時の給付金等にも、
可哀想だからなのかなど真っ直ぐな疑問を持たれています。
(大西)
手帳を取得して、1年ちょっとで、福祉制度の恩恵を素直にありがたく
受け入れられるようになった。とはいえ、一番大事なのは、
私の気持ちではなく、娘本人です。
そこで、この恩恵の事は本人が理解できてもできなくても、
全て説明しなければいけないと。
給付金が出た時は、
「中学校からは支援学級に入ります。
皆と違う作業を学び、将来働くために、
苦手な事も克服していかないといけないので、
応援してくれている市からお金を頂きました。
ちゃんと作業も嫌がらず、
みんなの気持ちに応えて頑張りましょう!」と。
その他にも、「放課後等デイサービス」など
障害のある子供たちのための福祉サービスは
本当にありがたく利用させてもらっています。
■娘は娘なので、制度の恩恵はありがたく享受し、
必要なことを考え、生きていきたい
(大西)
福祉制度の恩恵があるという意味で、
障害認定を受けて療育手帳を取得するメリットはあると思います。
でも、境界域にいる場合は手帳を取得する意味をよく考え納得する。
子供が小さい時は親がよく学び、考えてから取得すると良いと思います。
どうして取得するのか、取得するとどんなメリットがあるのか。
何のために取得するのか?考えることがたくさんあると思います。
同じような経験を持った先輩たちがきっとたくさんいるはずです。
そういう人たちの経験談を聞いて、よく考えて欲しいと思います。
療育手帳が取得しやすく、福祉環境が良い地域に引っ越した
という人の話も聞きました。
娘の場合は検査結果のIQで判定されたようですが、
たった2回の検査で何が分かるのか?
とも思います。なぜIQで決められなければならないのか?
とこのようなシステムに怒りを感じ、落胆していました。
でも、最近は、そんな怒りの感情にエネルギーを使うのは
もったいないと。主人が言っていたことを思い出したんです。
手帳の有無で、娘は変わらない。
やらなくてはいけないことは、
やらなくてはいけない。
だからこそ、現状を受け容れ、
福祉の恩恵をありがたく頂戴しながら、
娘と料理をしたり、刺繍をしたり、勉強をしたり。
周りに感謝し、娘にとって何が必要なのか
を考えながら生活していこう!と
思えるようになりました。
現実から目を背けなかった障害受容の過程
軽度の知的障害の中学生に「障害者」と言う自覚はあるのか?
大西さんは、大西さんと私のご縁を繋いでくれた
聴覚障害者でユニバーサルデザインアドバイザーの松森果林さん
と出会ってから、お嬢さんの障害の受容がスムーズにできたそうです。
ですので、周囲にお嬢さんの特徴をはっきり伝え、
お嬢さんにも周りから受けるサポートについて伝えるなど
隠さずに育ててこられました。
今後の課題はインクルーシブ教育
(島本)
IQの数値により知的障害を判定する意義は
線引きすることにより、
福祉で救済することにあると思います。
ただ、逆に線引きすることで
生きづらさが生まれているならば、
これは制度のあり方が問われてしかるべきと思います。
それに伴い、障害があることで
分け隔てられる事があると思います。
この辺りのことについて保護者の立場からの見解をお願いします。
(大西)
私が今、保護者の立場から強く思うことがあります。
それは、人が成長していく過程の基本は、
子供時代にあるということです。
人間が育っていくとき、まず、家庭で育まれ、
保育園、幼稚園、小学校、中学校・・・と続いていきますが、
そこで育った人間が社会を創っていきます。
社会を創っていく人間を育てるのが、
学校教育(義務教育)だと思います。
小学校1年生になり、
椅子に座って机に向かい、
じっとして先生の話を聞けない子供は
教室にはいられません。
そこに、聞こえない子、見えない子、じっとできない子がいたとしたら・・・。
言葉が理解できない子がいたとしたら・・・。
車椅子の子がいたとしたら・・・。
就学時前検診でふるいにかけられ、
就学時検討委員会で支援学級に振り分けられます。
その後は支援学校の子供と普通学級の子供と、
全く別の道を行くと言われました。
ですので、そんな現状を聞かされると、
発達障害のグレーゾーンにいるのなら
無理をしてでも隠せるものは隠したい・・・。
この親心はよくわかります。
みんなと同じように、
みんなと同じように・・・。
そう願うのが親です。
うちの場合はちょっと違って、
おとなしく座っていられる子で、
障害がとてもわかりにくかったです。
ですので、逆に、私が声を大にして、
「サポートしてください!」
とお願いしてきました・・。
ちょっと複雑ですね・・・。
(一般的にはうちのような場合、
親が認めず、隠し通して)
中学校ぐらいで、問題が
顕在化するパターンが多いようです。
で、何が言いたいかというと・・・・
学校教育がもっと変わってほしいのです。
先生も、教育制度を作っていく人たちも
グレーゾーンの子や障害のある子について
知らないことがたくさん。
当事者が声をあげ、当事者が語り、
一緒に考え、変わっていって欲しい
と思っています。
学校は担任の先生が1年間、
2年間で変わっていくことがほとんどです。
校長先生もそうです。
きちんと引き継ぎがされず、
継続性が断たれる事例が多くあります。
しかし、子供たちは小学校6年間同じ学校にいます。
その先も同じ地域の中学校にいるんです。
大きく育つ9年間。
様々な事を継続して学べる、大事な時期。
いろんな子供と一緒に育てば、
いろんな人間に対応できる社会を
創っていくことができると思います。
大きく先を見据えた教育ができればと思っています。
今、少しずつ浸透しつつあるインクルーシブ教育が
本当にできたとしたら、
社会は違ったものになるはずだと信じています。
投稿者プロフィール

-
知的障害&自閉症の娘を持つ母
卵巣がんと共存人生
手話通訳士に憧れる井戸端手話の住人
専業主婦天然枠代表