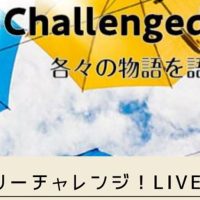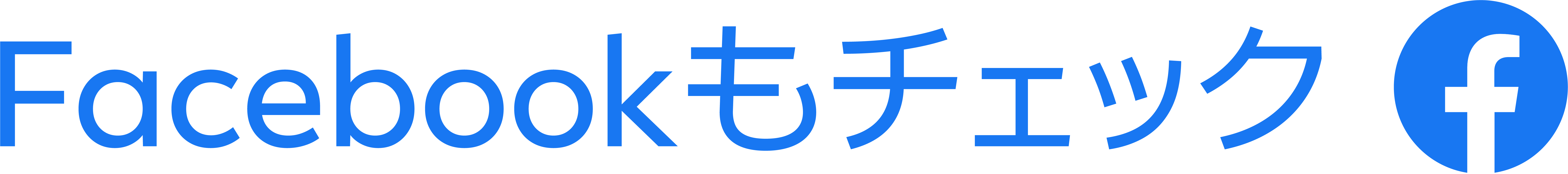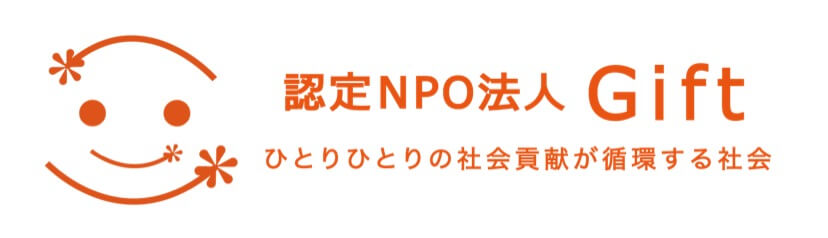バリアフリー、ユニバーサル対応は ビジネス上の利益を生む
こういう活動をしているので、障害やバリアフリー、ユ
ニバーサル等の言葉のついた研修や講演会などに参加しています。
私がこのような活動をするきっかけを作ってくださった竹中ナミさん(ナミねぇ)
の講演も何度か聴いています。
ちなみに、ナミねぇレベルの著名人の映像は、ネットで見ることもできます。
しかし、当然生での体験には敵いません。
さて、ナミねぇは講演において、今後の人口動態予測やそれに伴う社会保障の課題を踏まえた上で、
いかにして支える側の人間を増やし、日本を持続可能な社会にしていくか
を論理的に考え、その支え手としてのチャレンジドの可能性に着目したというマクロのお話をされます。
その上で、「チャレンジドを納税者に」という人によっては過激に映るスローガンを掲げて
ご自身がされてきたチャレンジドの就労支援についてお話になります。
偉そうな書き方になりますが、
活動の出発点にご自身が重症心身障害のあるお嬢さんを残して
安心して死ぬためには、「納税者を増やさなあかん」というパーソナルな要素もあるので、
活動が更に共感を呼んでいる部分があると感じます。
チャレンジドの可能性を発見して、
チャレンジドのことを「飛んで火に入る夏の虫」と表現されていました(笑)
文字にするとすごいですが、ナミねぇの関西人を通り越したラテン系の
軽快なトークの場合は大丈夫。
また、従来の福祉は閉鎖的なイメージでとにかく保護一点張りだったが、
そうではない「弱者を弱者でなくしていくプロセスこそが福祉や!」
と自らの哲学を力強く語られます。
この哲学に賛同するものですが、実現するためには、
チャレンジド側のスキルアップとバリアフリー化、ユニバーサル化
といった社会の側の配慮双方が必要です。
ナミねぇが講演でおっしゃった「福祉分野は神聖視されがちだが、
やっていることがきちんとビジネスになった方が広がる」
という主旨の話が今回の記事のベースにあります。
核心部分に話を進めます。
メーカーなどの企業は当然設備投資をしていますし、
個人事業主でも広告宣伝等に投資します。
バリアフリー、ユニバーサル対応には
これらと同等の効果が期待できます。
つまり、ビジネスになります。
今後激増する高齢者はお元気でも加齢に伴い、
私のような肢体不自由の身体障害者にある移動困難
に相当する課題に直面するのは自明です。
既存の障害者、今後高齢者になる方々を意識して小売業や飲食業などは
このニーズに対応するために店舗整備等をしておく必要があります。
商品力が無ければそもそも勝負できないにしても、
バリアフリー対応は、今後リピーターづくりのポイントになり得ます。
障害があると「行きたい」よりも「行けて快適かどうか」が選ぶ際のポイントになるからです。
現状全ての店舗がばりあふりーではないので、差別化を図れます。
早めに対応できれば利益に繋がります。
ハード面での対応には資金が必要なのでソフト面の強化から行うことは現実的です。
このような中で、ナミねぇが活躍しているチャレンジドとして、
(株)ミライロの垣内俊哉社長を講演で紹介されました。
ミライロはは今回書いたソフト面の配慮をユニバーサルマナーという形で体系化し
事業者に提案されています。
私自身もその講座を受講しましたし、当時同社の看板講師として活躍中だった
岸田ひろ実さんにインタビューをするご縁にも恵まれました。
さて、ナミねぇは私が参加した講演の残り10分くらいでで垣内さんを紹介した後、
「実は今日色んなチャレンジドにインタビューして、メルマガに書く
という取り組みをしているチャレンジドが会場に来ています。
彼は私のところにも話を聞きにきたことがあります」
と残り数分で私にマイクを渡すという荒業を使いました。
私は垣内さんのことを知っていたので、
「垣内さんの後で?」と一瞬思いました。
しかし、「おいしい」と思い直し、
自己紹介をさせて頂き、終了後、数名の方と名刺交換できました。
このように意欲を持って動いているチャレンジドをこんな風に無条件で応援されるのはナミねぇの投資でしょう。
投稿者プロフィール