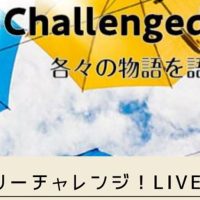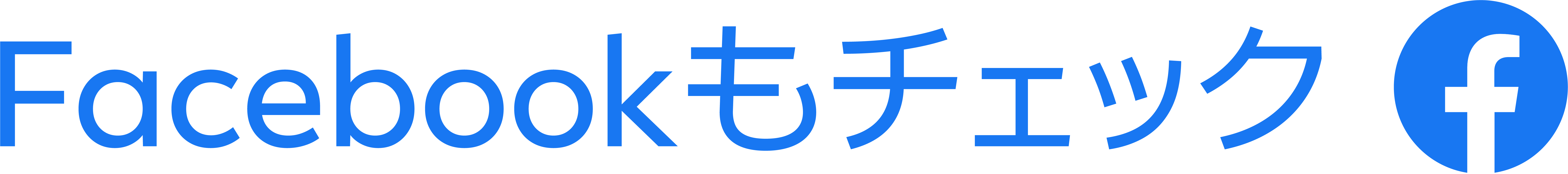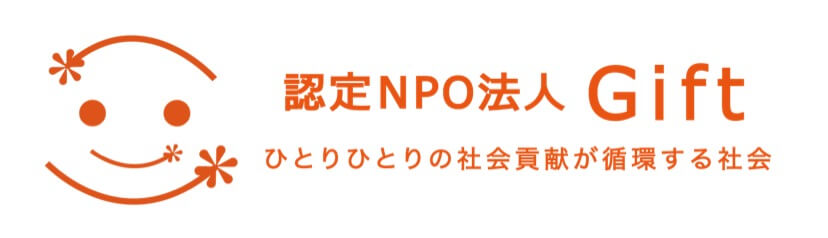私が手話講座に通い始めたきっかけ
昨年の今頃、インタビューから生まれた企画に
私はリーダーとして関わっていました。
ろう者(聞こえない人)と聴者(聞こえる人)が共創する日本唯一のプロ人形劇団
「デフ・パペットシアター・ひとみ」の宝塚公演です。
私は主催者側の実行委員長を務めたのですが、
そうなった経緯を簡単に。
劇団の制作スタッフ・大里千尋さんへのインタビューを
メルマガで配信したところ、
宝塚の読者様が公演招致に大変興味をもたれました。
きっかけが私のインタビューということもあり、
バリアフリーチャレンジ!としても公演に協賛し、
実行委員長をお引き受けしました。
ところで、5名の聴覚障害者の方に
私はこれまでインタビューさせて頂いた経験があります。
そして、聴覚障害者の関係者である大里さんへのインタビューを経て、
直接当事者(人形劇団)の 公演招致の責任者になりました。
過去のインタビューを通じて「手話ができたらなぁ」
という思いで独習を試みるも頓挫していました。
しかし、当事者に関わる責任者の立場になり、
本気でやるタイミングが来た、と思いました。
手話通訳士が主催者側の実行委員に加わって頂く
というご縁にも恵まれ、
まずは手話サークルに数回通ってみました。
聞こえる方がサークルメンバーには多いのですが、
基礎講座の修了者以上のスキルのある方々で構成されていて
活動時間中は音声言語を使わない方針で運営されています。
「しーん」
活動時間内は静寂の音が聞こえてきそうです。
私は 基本的にうるさいのが苦手なので、
その会議室の空気が私に何とも言えない心地良さを感じさせました。
静寂の中で皆さんが忙しく手を動かされているのですが、
唯一の初心者ですから何のことか全く分かりません。
それでもひるまないのが私の取り柄。
過去にメールでインタビューさせて頂き、
私に聴覚障害のあれこれお教えくださった松森果林さんが出演されている
NHKEテレの番組「ワンポイント手話」は欠かさず視聴してきました。
更に、デフパペの代表・善岡修さんが講師の
「みんなの手話」でかじったことを思い出しながら
何とか”片言”ながらでも理解しようと努めました。
音声言語無しで理解できるのかというと
それはさすがに不可能なので
近くの方がひそひそと通訳してくれる
「合理的配慮」はありました。
手話サークルでご縁を得たろうの方が
実行委員会に加わって下さったことで
私の音のない世界で生きる人への関心は更に高まりました。
その後始まった市の基礎講座へ申込み、修了。
更に中級講座に進み、現在も継続的に学習中です。
ちなみに、皆勤。私は左手を動かせませんが、 片手だけでも手話は成り立ちます。)
ところで、お二人のろう者が実行委員会に入られる際、
顔合わせの場を設けました。
会場が居酒屋風だったこともあり、
結構うるさくて音声言語同士の会話が成立しにくい状況でした。
通訳士の方を含めると、手話を使えるメンバーが4人いたので、
彼等は手話で会話していました。
通訳士の方が私の耳元で、
「こういう時に便利なのよ」と。囁きました。
その時、聞こえないことに秘められた
ある種の強さを感じました。
音声言語が主の社会では、
聞こえないことは障害と見なされます。
しかし、賑やかなで他の人が手話を使う状況では
手話を使えないことが障害とも言えます。
他にも興味深いことがたくさん。
聞こえなくても完全に音がないという訳ではないようです。
失聴している場合でも、耳鳴りというのはあるらしいのです。
また、ろうの方に通訳の方を通して
コミュニケーションをとった際、
振動で音を感じるし音の高低は何となく分かるという話も聞きました。
障害はない方がいい。
しかし、チャレンジドである以上は
はそれと向き合って私達は生きて行かざるを得ません。
手話言語の使用で聞こえる人より強くなれる場面もある
という見方は大切にしたいです。
この企画に参加したことで
聴覚障害のあるチャレンジドが
がどのように生きていらっしゃるのか、に
より関心を持てるようになりました。
生き方を知るには直接的なコミュニケーションが不可欠です。
その手段の一つとして学び始めた手話も
それなりに使えるようになってきました。
投稿者プロフィール